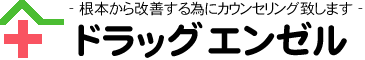長崎市内でダイエット相談を中心に慢性病や痛みの漢方相談を通して、皆様の健康をサポートさせていただいておりますドラグエンゼルの城尾寛樹です
🌿 はじめに:その「なんとなく不調」は気温差のせいかも?
最近、
「朝は冷えるのに昼間は暑くてダルい」
「なんだか胃の調子が悪い」
「よく眠れない」
そんな“はっきりしない不調”を感じていませんか?
もしあなたが40〜60代なら、それは単なる気のせいではなく——
👉 寒暖差疲労 かもしれません。
この年代は、更年期によるホルモンバランスの変動で、
体温調節の司令塔「視床下部」が疲れやすく、
若い頃より寒暖差の影響を受けやすいのです。
この記事では、
💠 西洋医学(自律神経)と
💠 東洋医学(漢方)
の両面から、この不調の正体と対策をわかりやすく解説します。
🌡️ 寒暖差疲労の正体(西洋医学の視点)
疲労の根源は「自律神経のフル稼働」
私たちの体には、
体温・血圧・心拍を自動調整する「自律神経」という仕組みがあります。
-
交感神経:活動モード(熱を逃がす)
-
副交感神経:休息モード(熱を守る)
朝晩と昼間の気温差が大きいと、
「暑いから下げろ!」「寒いから上げろ!」と
この自律神経が休む間もなく働き続けるため、
体も心もオーバーワーク状態に💦
🚨 40〜50代が注意すべき症状
| 症状 | 生理学的な解釈 |
|---|---|
| 胃もたれ・吐き気 | 交感神経の緊張で消化器官への血流が減少 |
| めまい・頭痛 | 血管の収縮・拡張が不安定になり脳血流が乱れる |
| 体重増加 | コルチゾール増加により内臓脂肪が蓄積 |
つまり——
寒暖差疲労への対策は「ダイエット」や「代謝維持」にも直結するのです。
🍵 身体を根本から整える(漢方の知恵)
「気・血・水」のバランスがカギ
漢方では、
体を支える3要素「気(エネルギー)・血(栄養)・水(体液)」の乱れが不調を招くと考えます。
寒暖差はまず「衛気(えき:バリア機能)」を消耗し、
次に「脾胃(胃腸)」を弱らせます。
胃腸が弱ると、
「気・血・水」の巡りが滞り、
➡️ めまい(水滞)や倦怠感(気虚)を引き起こすのです。
🍚 胃腸をいたわる“白い食材”が救世主
| 食材 | 効果 |
|---|---|
| 白ごま | 「気」を補い、エネルギー回復を助ける |
| 大根・かぶ | 胃腸の働きを助け、水の巡りを整える |
✅ 冷たい飲み物・生野菜を控える
これが漢方的セルフケアの基本。
胃腸を冷やさず「気」を生み出せば、自律神経も安定します。
🛁 今日から始める「自律神経安定化」チェックリスト
👕 ①「3つの首」と肩甲骨を守る
-
首・手首・足首を冷やさない
-
肩甲骨まわりを温める(カイロや温かいインナー)
👉 このエリアを温めると血行が改善し、自律神経の過緊張をやわらげます。
🛀 ② ぬるめの入浴で「副交感神経」をオン
-
お湯は38〜40℃
-
15分ほどゆっくり浸かる
熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激して逆効果です。
🌬️ ③「吐ききる」深呼吸でリセット
-
軽く両手を握って背中側へ引く
-
鼻から4秒吸う
-
口から8秒かけてゆっくり吐ききる
-
最後に両腕を上げて全身をリリース
「緊張→弛緩」の呼吸法は、自律神経のリズムを整える最高のセルフケアです。
🎁 まとめ:季節に負けない身体づくりを
「寒暖差疲労」は、体の“無理がきかなくなってきたサイン”です。
今日から、次の3つを意識して生活に取り入れてみましょう👇
1️⃣ 温める:首・手首・足首・肩甲骨を守る
2️⃣ 整える:ぬるめの入浴と深い呼吸で副交感神経をON
3️⃣ 養う:白い食材で胃腸をいたわる
💖 無理なく続けられる小さな習慣が、
「元気で美しい体づくり」への最短ルートです。
今夜はぜひ、
いつもより少しぬるめのお風呂にゆっくり浸かってみてください♨️