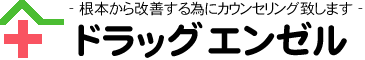長崎市内でダイエット相談を中心に慢性病や痛みの漢方相談を通して、皆様の健康をサポートさせていただいております。ドラッグエンゼルの城尾寛樹です。
ジメジメと湿度の高い日が続くこの季節。朝起きるのが億劫だったり、体が鉛のように重く感じたり、どうもやる気が起きない…そんな風に感じていませんか?
「年のせいかな?」「梅雨だから仕方ないか」と、つい見過ごしてしまいがちな不調ですよね。これは決して体が悪いわけではなくて、むしろ、あなたの体が「そろそろケアが必要ですよ」と、優しくサインを出してくれているんですよ。
漢方では、このような体の重だるさやむくみを「湿邪(しつじゃ)」という、外からの湿気の影響による不調と捉えます。今日は、この「湿邪」の正体と、日々の食事でできる具体的な解消法について、じっくりお話ししていきますね。
あなたの体からのサイン:「湿邪」って一体何?
梅雨の時期は、空気中の湿度が非常に高くなりますよね。この高い湿気は、知らず知らずのうちに私たちの体の中にも侵入し、余分な水分や老廃物として溜まりやすくなってしまいます。これが、漢方でいう「湿邪」の正体です。
例えるなら、体の中に重たい水を含んだスポンジがぎゅっと詰まっているような状態。体全体の巡りが悪くなり、様々なサインとして現れます。
- 体が重い、だるい:特に午前中や、体を動かし始める時に感じやすいかもしれません。
- むくむ:顔や手足がパンパンになる、靴下の跡がなかなか消えない、といった経験はありませんか?
- 食欲がない、胃がもたれる:湿邪は特に消化器系(漢方では「脾(ひ)」と呼びます)の働きを弱らせるため、胃腸の不調が出やすい時期なんです。
- 頭がボーッとする、スッキリしない:まるで霧がかかったように、頭の回転が鈍く感じることもあります。
もしこれらのサインが当てはまるなら、あなたの体は「湿邪」の影響を受けている可能性がありますね。
「湿」を追い出す食事術:カギは「利水」と「健脾」
では、この体の中に溜まった「湿」をどうすれば追い出せるのでしょうか?ポイントは大きく二つ。
一つは、余分な水分を「排出(利水)」すること。もう一つは、消化器系(脾)を「元気にする(健脾)」こと。この二つのバランスを意識した食事で、体はぐっと軽やかになりますよ。
1. 余分な水分を「排出(利水)」する食材で“湿”を流しましょう
体内の余分な水分を外に出す手助けをしてくれる食材はたくさんあります。利尿作用のあるものを積極的に取り入れてみてください。
- きゅうり、冬瓜(とうがん)、ナス、もやし(緑豆もやし):これらは体内の熱を冷まし、同時に余分な水分を排出するのを助けてくれる夏の救世主のような存在です。特に冬瓜は、むくみ対策にとても頼りになります。
- あずき、ハトムギ、とうもろこしのヒゲ(南蛮毛):これらも優れた利尿作用を持つ食材です。あずきは煮汁ごと、ハトムギはお茶やご飯に混ぜて、とうもろこしのヒゲはお茶として、生活に取り入れやすいですね。
- セロリ:香りで気の巡りを良くし、頭重感やイライラといった湿邪による不調を和らげる効果も期待できます。
- 昆布:粘り気のある老廃物(痰湿)を取り除き、むくみ体質の改善にも役立ちます。
- スイカ(特に皮の部分):果肉は体を冷まし、水分を排出する作用がありますが、薬膳では皮を「西瓜皮(せいかひ)」としてむくみ解消に活用します。
これらをスープやお粥にすると、胃腸に負担をかけずに優しく摂ることができますよ。
2. 胃腸を「元気(健脾)」にして湿気をさばく食材をプラスしましょう
湿気が体に溜まる背景には、胃腸の機能が少し弱っていることが隠されていることが多いです。消化を助け、脾の働きを高める食材も意識して取り入れてみてください。
- 大葉、生姜、ミョウガ、山椒:これらの香味野菜は、気の巡りを良くし、消化促進を助ける働きがあります。食欲が落ちやすい時期にも、料理に心地よいアクセントを加えてくれますね。特に生姜と大葉は、湿気を“散らす”力にも優れています。冷やしそうめんや冷奴に、薬味としてたっぷり使うのがおすすめです。
- 梅干し(適量):酸味は唾液の分泌を促し、食欲増進や消化を助ける働きがあります。
3. 冷たい飲食で「湿」を呼び込まない工夫を
梅雨の時期は、ついつい喉越しが良い冷たい飲み物やアイスクリームに手が伸びてしまいますよね。もちろん、一概に全てが悪いわけではありませんが、摂りすぎには少し注意が必要です。
なぜなら、冷たいものは胃腸を急激に冷やし、その働きを弱めてしまうからです。結果として、体内の水分代謝が滞りやすくなり、せっかく排出したい湿邪がさらに溜まりやすくなってしまう可能性があります。
- 氷入りの飲み物よりも、常温か温かいお茶(ハトムギ茶、黒豆茶、生姜茶など)を選ぶようにしてみましょう。
- アイスなどの冷たいデザートも、少量にしたり、温かい食事の後に摂るなど、体を冷やしすぎない工夫を心がけてみてください。
「我慢より、納得が続く」という私の指導ポリシーの通り、無理にすべてを断つ必要はありません。体が「心地よい」と感じる範囲で、少しずつ調整していくことが大切です。
実践編:おすすめレシピで“湿抜き”習慣を!
ここからは、日々の食事に無理なく取り入れられる、湿をさばく薬膳レシピをいくつかご紹介します。
🍲【レシピ①】冬瓜とあずきのやさしいスープ
~むくみ・だるさを一掃する、シンプルで効果的な一杯~
材料(2人分)
- 冬瓜:200g
- あずき(ゆで):50g(市販の水煮缶でもOK、無糖のものを選びましょう)
- 生姜(千切り):1かけ
- だし汁(味わい出しがBEST):400ml
- 薄口しょうゆ:小さじ1
- 塩:少々
作り方
- 冬瓜は皮をむき、種とワタを取り除いて一口大にカットします。
- 鍋にだし汁、生姜、冬瓜を入れて火にかけます。
- 沸騰したら弱火にし、冬瓜が柔らかくなるまで10分ほど煮ます。
- ゆであずきを加え、さらに5分ほど煮込んだら、薄口しょうゆと塩で味を整えて完成です。
🔸ポイント: 冬瓜とあずきの「利尿コンビ」が、体にたまった湿をしっかり流してくれます。生姜が加わることで、胃腸を温め、消化を助ける効果も期待できますよ。
🍚【レシピ②】生姜と大葉の梅風味あずき粥
~湿をさばき、心も体も整う朝ごはんに~
材料(2人分)
- ご飯:お茶碗2杯分
- ゆであずき:50g
- 水:400ml
- 生姜(すりおろし):小さじ1
- 梅干し:1個(種を取り除き、たたく)
- 大葉:3枚(千切り)
- 塩:ひとつまみ
作り方
- 鍋にご飯、ゆであずき、水を入れて火にかけます。
- 沸騰したら弱火にし、生姜と梅干しを加えて7〜8分ほど煮込み、お好みのとろみになったら火を止めます。
- 塩で味を整え、器に盛り付けたら、最後に大葉の千切りを散らして完成です。
🔸ポイント: 朝から胃腸に優しく、体を内側から温めてくれるお粥です。生姜と大葉が湿気を散らし、梅干しが消化を助けてくれます。心の落ち着きにもつながりますよ。
☕️【おまけ】湿を流す薬膳ティー
普段の水分補給として、ハトムギや黒豆、薄切りの生姜を一緒に煮出して作る「湿出し茶」もおすすめです。保温ポットに入れて持ち歩けば、いつでも温かく、むくみやだるさ対策に役立ちます。
まとめ:湿邪対策は“軽やかさ”と“温かさ”がキーワード
「梅雨だる」は、決して体調が悪いというわけではなく、あなたの体が「湿気が溜まってきたよ、ケアしてね」と教えてくれている大切なサインです。
このサインをしっかり受け止めて、日々の食生活を少し見直すだけで、体はきっと軽やかさを取り戻してくれますよ。
- ✅ 利尿作用のある食材で水はけを良くする
- ✅ 消化を助ける薬味で胃腸を元気にする
- ✅ 冷たい飲食を控え、体を冷やさない工夫をする
- ✅ 今回ご紹介したレシピを味方に、日々の習慣に取り入れる
無理にすべてを変えようとしなくても大丈夫です。体が「だるい」と感じることは、ある意味、体からの賢いメッセージなのです。そのメッセージに耳を傾け、自然のリズムと調和しながら、ご自身のペースで少しずつ体を整えていきましょう。
もし、これだけでは改善しない場合、できないことが多い場合は漢方薬を上手に取り入れてくださいね。
何かご不明な点や、さらに詳しく知りたいことがありましたら、いつでもお気軽にご相談くださいね。